Contemplation Field of MichiroJohn
Chapter3-1
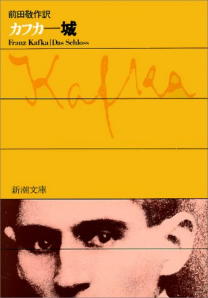 �@
�@ �@
�@ �@
�@
The Castle (1926)[a] by Franz Kafka (1883-1924)[b] Kafka (19�X�P)�@[��] by Steven Soderburgh[d]
�@�O�͂ł������q�ׂĂ������A�J����̘b����ِ��l�̕��ʂ����݂Ă݂�B�����Ă��̔w�i����J���炪���݂��闝�R�Ȃ莖��Ȃ���l���Ă݂�B����̓��[�g�s�A�l��m���ł��A�n�������ꂩ����������m���ł��d�v�Ȃ��ƂƎv��ꂽ�B�J����̘b�͞B�������ۓI�ł���A�Ȃ��؋��������Ȃ����A������Ă���b����n���Љ���ׂ������ւ̕������������������Ƃ͉\�������B���̕���͂��̂��߂̃X�g�[���[�ł�����B���̕�����������������悤�ɗU�����Ă��郂�m���J����̒��ɂ͂���B�J���炪�{������ׂ��́w�n���Љ�������ׂ������ւ̎w�j��^����x���Ƃ������̂��낤�B�J����͂��̌��Ɋւ��āA���Ȕ��Ȃ��܂߂ėl�X�Ȍ������ِ���J��Ԃ��Ă��邪�A�v�́[�[�[
�w�����N�����o�邤���ɃJ����͕ϗe���Ă��܂����x
�Ƃ������Ƃ��B���ł͂�����������ʂ�z���āA�����̈������B���Ȕ��f�\�͂������Ă��܂��Ă���Ƃ����Ă������B
�@�J���炪�����ɐ��艺����ߒ��͂܂�Ƃ��땪����Ȃ����A�J����̌�����悭�������b��ł�����̂ŁA�z�����邱�Ƃ��ł���B���n���ɑ������������̂悤�ɂȂ��Ă��炤���Ƃ�����Ęb���Ă���A�܂�J����̍����̂P�ƍl�����邪�A�J����̒��������o�[���b��ɏ���Ă���悤�Ȃ̂ŁA�N�ނ̓��肪����Ȃ�`�Ō���Ă��邱�Ƃ������B�J����̎��Ƃ��ē����Ă����Ǝv����A���h���C�h���������������o�[�̈ӎv��`����`�œ`�����Ă���[�[�[�Ƃ������������B����͉B���Ă���悤�ŁA�J����̌����̎Љ�`�Ԃ����̂܂ܓ`����`�ƂȂ��Ă���Ǝv���A��ώQ�l�ƂȂ�B���A���������n���l�����̂悤�ɂȂ��ė~�����Ƃ����J����̍����ƍl������̂Œ��ӂ��K�v���B
�@�J���炪����������ߒ��������z�������͈͂ł́A
�[�[�[�����N�����o�邤���ɍ��Ƃ̘g�g�݂������Ȃ�A�������͌`�[�����܂��ƁA�l���x���ō��ƃ��x���̂��Ƃ��s����悤�ɂȂ����B�푈����i�}�C���h�R���g���[���j�A�͂Ă͘f���P���_���}�ɕς��Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ��l���x���ʼn\���B���̌��ʁA�@����`�͖��O���x����������悤�ɂȂ�A���ƁE�g�D�����Ă����������Ő��藧���Ă����l�̍s���K�͂��Ȃ��Ȃ�A�������������n�U�[�h���Љ�ɖ��������B�l�Ԃ̎Љ�I�ȊW�͂��͂���Ȃ��Ȃ�A�l�͕������肪���A�o�ς͒�����ƂȂ�A�Љ�͗L�@�I�ɋ@�\���Ȃ��Ȃ����B���̂悤�ȎЉ�ɂ����Ă͈����I�ȍs�������邱�Ƃ��B��̃J���t���܂ł���A�l�������`�x�[�V�����ɂȂ������B
�[�[�[�Ƃ������Ƃ��B
�@�Ȃ��悭������Ȃ��Љ���A�l�ɖ��f�������邱�Ƃ��Љ�̌��S���ɂȂ���ƃJ����͐M���ċ^��Ȃ��̂ŁA�J����͂��̂悤�Ȑ��E�̏Z�l�ł���Ƃ������Ƃ��B
�@�s���l�����J����̖����Љ�ɂ����āA�B�ꊈ���I�������̂͂����Ĕƍߍs�ׂ��s�����ƂŃR�~���j�e�B�[�̌�����}�낤�Ƃ���W�c�������悤���B���㕗�ɂ����ƁA�w�s�ǃO���[�v�x�Ƃ��w�t�[���K���x�ƌĂ����̂��B�����ǐ��V�X�e���ɂ݂���O�ꂵ���Ǘ��Љ�ɂ����āA�V�X�e���̊Ď��������������Ĕƍߍs�ׂ��s���Ă݂��邱�Ƃ͋`���I�ȏ^���邱�ƂƂȂ����B�x�@�@�\���}�C���h�R�����[���e���������A���̑{���i�i�m�e�N�{����l�L���{���j���s���Ă��邽�߁A�����ƍ߂��N�������߂ɂ��k�ق�M�����ِ�ōs�����ǂ�|�M���A�����I�ȋ삯�������s���K�v���������B�����ɑ��ł͖��킦�Ȃ��y���݂��������Ƃ����Ă����B��ɔƍ߂��N�����Ȃ��͂��̊Ǘ��Љ��ł��j���Ă݂��邱�Ƃ��J����̐��������ɂȂ����̂��B���ꂪ���O���x������̖@����`�̕���ł���A�J����̊Ǘ��Љ�ł͋t�ɔƍߍs�ׂ����������B�Љ�S�̂��݂Ă݂Ă��A�������w�ɔƍߏW�c�����݂��Ă��邾���ł͂Ȃ��A��w���܂�A���h���C�h�������k�ق�M���č��@�I�Ȕƍ߂�Ƃ����Ƃ����̂ŁA�Љ�S�̂������ǐ��V�X�e���ɓG���Ă���Ƃ������B����������V�X�e���͋t�ɐl�X�ɕs���S�ȕ��̍l��������N���Ă��܂��Ă����Ƃ������ƂȂ̂��낤�B
�@�J����͒����ǐ��V�X�e����j�邱�Ƃ��x�X�������悤�����A�V�X�e���Ɉˑ����Ă���J����̓V�X�e�����甲���o�����Ƃ͏o�����A���������̍s�������Ȑ������������ŁA���ǁA�O�G�����Ȃ����Ƃɖ�肪����Ƃ������_�ɒB���Ă����悤���B��������͂��Ȍ��_�ŁA���͂Ƃ̗ǂ����C�o���W�����Ȃ��l�Ԃ����B�����c���z�������B�J����͂��łɒ��l�I�ł���A���C�o�����R���Ƃ����@�ɂ͏n�m���Ă����B�J����͐_�ł���A���C�o���͂��Ȃ������B�ǂ����C�o�������Ȃ����߂Ɏ������������h���ƂȂ���̂ɖR�����A�₪�ĎЉ��u�₵�ĕ������邩�A�t�ɒ��˕Ԃ��Ē������ق��ɑ��邵���Ȃ��悤�������B�J����͌��ǁA�̈ӂɁw���҃`�[���x�Ȃ鍇�@�I�ȔƍߏW�c���`�����邱�ƂŎЉ�̃J���t���܂Ƃ���s���ɏo�Ă����B�J����͈����I�ȍs�������邱�Ƃő���Ƃ̂Ȃ����ۂƂ��Ƃ���A�c�ΐl�W�̍\�z��}���Ă���l�Ԃ�������グ�Ă����Ă����B
�[�[�[���̌��ʂ��A�������ɂ���̂��낤�B
�@�J����͖@����`�̐��E�ɂ͓���߂Ȃ����A����𗥂�����̂��Ȃ��Ǝ���̈����I�ȍs���𐧌����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA�@����`�̂�������Ƃ������E�Ɋ��悤�Ƃ���[�[�[���ꂪ�����J����̐N���̗��R�ł���A�w�ڏZ�x���낤���A���ꂾ���ł͑S�Ă�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��悤���i�����������ꂪ�ł��傫�ȗ��R���j�B�J����͉����Ɉˑ����Ȃ��Ɛ����Ă����Ȃ��q���̂悤�Ȃ��̂��B�J����̌�������́w��l�x�w�q���x�Ƃ�������ʂ̎d�����悭�s���Ă���A���������̐��E��m���Ă��邱�Ƃ��w��l�x�ł���A�m��Ȃ��Ɓw�q���x�ɂ���Ă��܂��B���g�̐l�Ԃ��w�q���x�ł���A�A���h���C�h�ɂȂ�Ɓw��l�ɂȂ�x�Ƃ�����ʂ̂����������B�w�q���x�̂ق����l����^�ʖڂɐ����A����ۂǗD��Ă���Ǝv��ꂽ���A�J����͂��̂悤�ȕ]���̎d���͂��Ȃ��B
�@��X�̐��E�ł͎q������l�Ɠ������������邱�Ƃ��厖�ł���A�q���ł���Ƃ���l�ł���Ƃ��ɂ������҂͑��͎q�����B�J����̒��͒����ǐ��V�X�e���ɐl�i��^���āw��e�x�ƌĂԎ҂�����A���̈ˑ����͑����Ȃ��̂ł��邱�Ƃ��z�������B�q�����N�����l����Ƃ���ȕ��ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B���������̍l�����͌��n�����w�q�����x���Ďx�z��e�Ղɂ��Ă��܂����Ƃ���J����̍����̂P�ƍl������̂ŁA���̂܂q���Ƒ�����̂͊댯���B���n�����q�������悤�Ƃ��邤���Ɏ����������q���̂悤�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����\�������邭�炢�̂��̂��B


AKIRA (1988)[h] by Katsuhiro Otomo[i]
THEIR future society seemed something similar like the world of AKIRA the movie.
�@�J����̖����Љ�ł́w���x�ɑ��鉿�l������n���l�̂�����������A�J����ɂ́u���������ɕ�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ���遂肪�������悤���B������Ȃ����Ƃ��Ȃ��̂Œm�I�T���S��������A�Љ�S�̂̃��`�x�[�V�������������Ă����B��������͕�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��Ə���Ɏv������ł��������Ȃ̂��낤���A���̂悤�Ɏv������̂��J����̒��ɂ͂������̂��낤�B����͌㑱�ِ̈��l�Љ�ɂ����Ă����l�������悤���i�����Ă������J����ɕt�����܂��X�L�ƂȂ����j�B�����N�����o�邤���ɃJ����̏��̈������͕ω����A�u������Ȃ����Ɓv����邱�Ƃ��厖�ƍl����悤�ɂȂ����悤���B���������邱�ƂłȂ��A�B�����Ƃ�厖�Ƃ����̂��B������Ȃ����Ƃ��Ȃ����E�ł͏��̉��l�͉������������A�����o������ɐ�����݂�����̉��l���オ���Ă���B����l�ł͈����Ƃ��v�������B�����A�J����̐��E�ł͍��@�I���D�ꂽ�s�ׂ̂P�Ƃ��ꂽ�B���������̏��𐧌����邱�Ƃɂ���ĎЉ�ɂ͖{���ƌ��O��������绂���悤�ɂȂ�A����ɂ�郂�����n�U�[�h����N���ꂽ�B�����A����͐l�������`�x�[�V�����ɂȂ�Ƃ��āA��莋���邱�Ƃ͂���ɂ���A�������߂�Ƃ������Ƃ͂Ȃ������悤���B
�@�������ăJ����̎Љ�ɐ^�����B���w��x���`�����ꂽ�B���̏ꍇ�A��ɏo����ł��邩�ǂ������w��l�x�ł��邩�A�w�q���x�ł��邩�̋��ڂ��B�n���E�b�h�f��w�J�t�J�^���{�̈����x�̎�l���悤�Ɂw��x�̒��ɓ��邱�Ƃ��ł���҂͂����킸���ŁA���������̏�ɓ��邽�߂ɂ̓A���h���C�h�����Ă��܂�Ȃ��Ƃ����Ȃ��悤�������B���g�̐l�Ԃł́A��O�łƂ₩�������Ă��邾���̎�l�����i����́w��x�̃X�g�[���[���j�A�������J�t�J��́w�R���x�̂悤�ɈӖ��s���ȍٔ��Ɋ������܂�Č��̂悤�ɎE����Ă��܂������̎�l���ɏI����Ă��܂��悤�������B


The Trial[e] (1927) The Trial[f] by David Jones[g]
People who forced to stand outside of " Das Schloss " have dropped into lower people, never their wish had come true. It was usual things that the lower people would have turned into a mob. People who could have become androids and turned into upper class fortunately would have run into crime usually. They would have tried to make a loophole against watching of The Central Control Unit ( CCU ). It was always the nettle for the upper class. For that CCU had kept controling to prevent from oppression of ruling class, upper class would have tried to break the system by using lower people. It would be much easiler than using power of authority. The lower class had started a riot, in the meanwhile, the upper class would have tried to expand their authority. CCU had preferred the perfect, the authority which was not the perfect would be reduced the power. It was natural of that they would have begun to struggle with CCU.
�w��x�̒��́A�e�X�g�ŃI�[���P�O�O�_������Ă݂���悤�ȘA���̏W�܂肾�����炵���B�ނ�̂悤�Ȑl�Ԃ������Ă���ƁA�ނ�������N�t�����ĕ��ʂ���K�v�������Ă������A���̃����N�t���͓���A���̐l���ɂ����ĎЉ�ɖ��f���������x�����Ń����N�t�����Ă����悤���B�s�����s�����Ƃ��A�푈�������Ƃ��A���B����������ł����f������Ȃ�i�I�[���P�O�O�_�����悤�ȘA�������������~�X��������̂ł��Ȃ��j�A�w�ߋ��ɐl�����܂����x�Ƃ��w���A�l�ɖ��f���������x�Ƃ��Ń����N�t�����Ē�����ۂ��Ă����悤���B�w��x�̓q�G�����L�[���Ȃ��ƒ������ۂĂȂ��قǂɔ�剻���Ă����Ă����B���̃����N�t���̓A���h���C�h���������_�@�Œǂ��l�߂Ă����A���X�P�ǂȎs���������A���h���C�h������ƍ߂ɑ��点�鈫���������N�������B�����V�X�e���Ƃ��̊Ǘ��҂ł���A���h���C�h�����́A�A���h���C�h�̐�ΐ������炷�Ƃ�����̑I�ʂ�����ōs���Ă����̂Ŗ��Ƃ��Ȃ������B�ނ�̖����Љ�̓A���h���C�h����Љ����Ă������Ƃ�����B
�@�l�����_�@�ŕ]�����Ă����Ƃǂ��������ƂɂȂ邩�A�[�[�[���C���������A�[�[�[���˕Ԃ��Ĕƍ߂ɑ��邩�A�[�[�[�������V�X�e���Ǘ��҂����͂�����Љ�����N���܂Ƃ��������Ȃ������悤���B�w���Y���s�l���܂������x�ŁA�V�X�e���Ǘ��҂�����Œǂ����Ƃ���Ă��������A����́w�@�B�̎����x�Ƃ������Ƃňӂɉ��Ȃ������B���Ȃ݂ɔނ�̎Љ�ł͎��Y���x�͔p�~����Ă����̂ŁA�w�L�^�����Y�x��w�j��Y�x���A���h���C�h�ɂƂ��Ă̎��Y�ɑ��������B���̂Q�̌Y���͖@�����ł͏����ꂸ�Ɋ��K�@�I�Ɏ{�s���ꂽ���߁A���ꂪ�ނ�̖@����`�����邫�������ƂȂ����悤���B���̊��K�@�̎{�s�ړI���w�Љ����ۂ��߁x��w�ĔƂ�h�����߁x�Ƃ������@���{�s�̖{���̈Ӌ`�Ƃ͈Ⴂ�A�P���Ɂu���̖�Y��ׂ��v�Ƃ������ړI�ŕ�`�I�Ɏ{�s����邱�Ƃ����������炵���B�G���[�g�͓G�������Ƃ������ƂȂ̂��낤�B

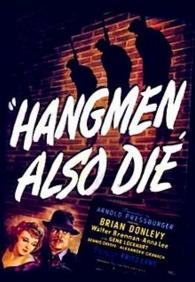
Hangmen Also Die ( 1943 )[j] �M��F �w���Y���s�l���܂������x�@by Fritz Lang[40]
�@�Љ��ǂ����邽�߂ɒ����ǐ��V�X�e���͑��݂��Ă���͂��Ȃ̂ɁA�V�X�e�����Љ���������Ă����Ăǂ�����̂��H�|�|�|����ȋ^�O���킢�Ă��邪�A�ނ�̎Љ�͐푈���Ȃ��Ȃ荑�ƌQ���P�ɂ܂Ƃ܂����Љ�ł���A�O�G�����Ȃ������B�O�G�̓e�����X�g�Ƃ��ėe�Ղɕ��ӂ����B�ނ�̎Љ�̓V�X�e����AI�������ďo�������������ȋʏ��̂悤�ɐU�肩�����A覐ΏՓ˂���Љ�x�̈����܂ł����h���ł݂���A�܂��Ƀ��[�g�s�A�������B���X�̑���N�����Ă��Љ�͗h�邪�Ȃ����A�܂��t�ɈӐ}�I�ɑ�����N�����Ă���肪�Ȃ������B���������̊���������Љ�͕ω��ɖR���������̂��낤�B�l�����Ă����̂��݂Ĕڋ��Ȋ�т������Ă����悤���B���̃J����������ł���B�ނ�͌��ǁA�l�������Ă����̂��~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�ނ�͔ƍ߂��ق��̂ł͂Ȃ��A�ƍߎ҂��ق��悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@�ނ�A���h���C�h�����͂��̈��s���������āw��x����Ǖ�����Ă��܂��ƁA�A���h���C�h�̔s�k�҂̏W�܂�ł���w���҃`�[���x�ɐg�𗎂Ƃ����ƂɂȂ����B�Љ�����J���t���܂Ƃ��ė��p���ꂽ�̂��B�A���h���C�h�ő�߂�Ƃ����҂́A�����ł��܂ł��ウ�ꂵ�ސӂߋ�����B�A���h���C�h�Љ�ł͎��Y�͐��g�̑̂������邾���ňӖ����Ȃ������̂ŁA����Ɂw���ҁx�Ƃ��ĉi���̐ӂߋ�𖡂��킹�悤�Ƃ����悤�Ȏ{���{����Ă����悤���B���̕��@�͒��ϓI�Ől�̐S������ł������A�ߌY�ʌY��`�ɂ��Ȃ���`�͂����ɔj�]�����B���́w���҃`�[���x�͌��X�P�l���P�l�炵����������悤�ɂƃV�X�e�������o�����A���`�e�[�[���������A
�[�[�[�_�͐�Ȃ̂ɁA�Ȃ����������݂ł���̂��H�[�[�[
�Ƃ����悤�ȓw���I�Ȗ��������킹�����Ă����B����́A�V�X�e�������o�������l�������ƍ߂�Ƃ����Ƃ���ƁA������ۂ͂��̃V�X�e�����Љ�ɑ��Ĕƍ߂�Ƃ����̂ł͂Ȃ����Ƃ�����肾�B
�@�V�X�e���͎Љ�ɑ���AI�����ōőP�̑I��������Ă����炵�����A�w�ő命���̍ő�K���x��I�����Ă��܂��Ƃ��낪����A�����ӌ����E���グ��̂�s���ӂƂ��Ă����B�����h�̈ӌ��ɂ��^���͊܂܂�Ă���A���l�̍s�����܂��l�Ԃ̏��Ƃ��ڂ��ӂ������B�ƍ߂͂��̎���̈��������̎҂�ʂ��đ̌����ꂽ�����̂��Ƃ��B
�@�����h�̈ӌ����E���グ�邱�Ƃ͏d�v���Ɣނ���l���Ă���A�V�X�e���Ǘ��҂ł���A���h���C�h������������s���Ă����悤�����A�����ɂ͓ƑP������A�������������Ă����B�����g�����ׂ����ď��Ƃ������o�����[�X�ɂȂ肪���������B�܂��A���l���������Ƃ���͔̂ނ炪��������łȂ��Љ��������Ƃ����l�����������Ă������A���l�͈�萔���܂��Ƃ��āA��萔���܂�Ă��鈫�l���ߋ��̑�ƍߎ҂��A���h���C�h�����Ă��Ă����悤�ɂ��Ă����悤���B�ƍ߂��N����Ƃ������Ƃ̓V�X�e���ɕs��������Ƃ������Ƃł���A�V�X�e�������O�ɔƍߎ҂�p�ӂ���Ȃǂ͖{���]�|�A�Љ��ƍ߂��Ȃ����Ȃ��Ȃ�V�X�e���͎Љ�x�Ɋ֗^����ׂ��ł͂Ȃ��[�[�[���̂悤�Ș_������A�V�X�e���͊��x�ƂȂ��j��Ă������A���ǁA�V�X�e���͂��̌��������ۂ��������悤���B�ނ�̓V�X�e���Ɉˑ��I�ɂȂ��Ă���A�܂��V�X�e�������O�x�z�̓���Ƃ��ėL�p�ƍl���鐭���I�o�C�A�X������ɉ���邱�Ƃɂ��A���v�w��ƍ߂͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��Ƃ����k�قɗ�����Ă��܂����悤�������B�l�̐l���͓��v�ł͂Ȃ����A�ƍ߂̔������������v�ł͔��f�ł��Ȃ��B�ƍ߂͐l�̐S��Љ�̕ω��ɍ��������̂��B�������V�X�e���͐��l�I�Ȃ��̂ł��������f���Ȃ������B����͂���Ӗ�AI�͐����ł����������f�ł��Ȃ��Ƃ������߂ł��������̂��낤���A������J��Ԃ����ƂŔނ�̖����Љ��͎��R�x�������Ă����A�l�X�Ȉ����������܂�Ă������B�V�X�e���͎Љ�����S�Ɉێ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����Ő����Ă��Ȃ��l�X�͂��C�������Ă��������A�V�X�e���Ǘ��҂����͎Љ�͕��a�ł���Ƃ��āA����ł������͕ۂ���Ă���Ɣ[�����Ă����炵���B���̎��_�Ŕނ�̎Љ�́w���a�I�Ɂx�敾���Ă����Ƃ�������B�����Ɂw��x����Ǖ����ꂽ�A���h���C�h���������荞��ł��Ď��Ԃ͂���ɂ�₱�����Ȃ����B
�@�܂��V�X�e���̖��Ƃ��āA�Љ���Ǘ����悤�Ƃ���Ɩ��O�̐l�C���ɑ����Ă��܂��Ƃ��낪����A�l�X�̊��S�����߂Ȃ�@����`���Ȃ�������ɂ��邱�Ƃ��܂܂������B��߂�Ƃ����A���h���C�h�ɉi���̋ꂵ�݂�^����Ƃ��������Ƃ����̓T�^���B
�@���҃`�[���ɗ������A���h���C�h�����̒��ɂ͂��̃V�X�e���̕s�����U�����āA���ԂƂ���R����҂������B�������A�ނ�̓V�X�e����j�邱�Ƃ͖����ɁA�����ɂ��ăV�X�e������S�����Ď����̌������Ƃ����邩�Ɏ������������B�ނ�̓V�X�e����������A�V�X�e���I�Ȓ�������Љ�ɕ��Q���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����B����Ӗ��A�ނ炱�������łȂ��l�Ԃ������Ƃ�����B���ʂ̃A���h���C�h�Ȃ�A���g�̍s���̂��ׂĂ𐔒l�����Ă݂��Ă����̉������B�ނ�͂���ȉɔ����͊����Ȃ������B�ނ�͖ړI��B�����邽�߂ɁA�����Ď��Ȃ̑��݂������������B����ے肵�ĕs���葽���̑��݂ɂȂ邱�Ƃɂ��A�N���ƍ߂�Ƃ����̂�����Â炭�����[�[�[���ꂪ�w�J����x���a���������������������炵���B�ŏ��͓O�ꂵ���e�������J���炾�������i�w�L�������Y�x��w�j��Y�x���҂��Ă����j�A�Љ�̃A���`�e�[�[�Ƃ��ĂȂ�Ƃ���w�������Ɏ�����A�ŏ��͂��̌�p��������n�߂Đ��͂�L���Ă������B�A���h���C�h�Љ�ɂ����ẮA��x�~�X��Ƃ��Ƃ��̑O���������i�����ĉ��Ƃ��낪����A�~�X���Ƃ��Ȃ��NJ����������B�������J����̐��E�ł̓~�X���Ƃ����肾�����B����Ӗ��A�l�Ԃ��ł��l�Ԃ炵����点��p���_�C�X�������̂�������Ȃ��B�₪�ď�w���������i��ŃJ����̒��ɓ����Ă����悤�ɂȂ�A��吨�͂ɐ������Ă������B���̖��͉͂��Ƃ����Ă�
�@�@�@
�w�ƍ߂̔Ƃ��₷���x
�@�@�@
�������悤���B��w�������͒������������āA�����܂Ƃ��Ȃ��Ƃɂ͋��������ĂȂ��Ȃ��Ă��܂��Ă����ɈႢ�Ȃ��B�V�X�e���̓J����ɂ������đË��_��T���悤�ɂȂ��Ă������B
�@����ɃV�X�e���͋@�\���Ȃ��Ȃ�A�Љ���@�\���Ȃ��Ȃ����B�Љ�ɂ͈��̉��ԊJ���A�A���h���C�h�����̓}�C���h�R���g���[����̑{���𗐗p�����ׂ��������J��L���������B�܂����g�̉��w�������͑唼���A���h���C�h������`�Ŏ��ɐ₦�Ă������B��������̑��A���h���C�h�Љ�ɂ����ẮA�w�}�C���h�R���g���[���x�w�i�m�e�N�E�L���[�x�w�u���[���E�X�L���j���O�x�́A����ΎO��̐_�킾�����B����炪�����炷���������ǂ��������Ă邩�ɁA���̂Ƃ��̐l�דI�Ȑ��K�v�Ƃ��ꂽ�BAI��������Ȃ��A�l�Ԃ̉��l���f���K�v�Ƃ��ꂽ�B�J����͂��̏ɑ�ϖ��������悤���B�V�X�e���͖{���̋Ɩ��A�l�Ԃ̕⏕���Ƃ���覐ΏՓ˂Ȃǂ̊댯�\���̋Ɩ��Ɍ��肳�ꂽ���A�K�v�ɉ����Ĉ��҂Ƃ��Ė��O�e�����s�����Ƃ����v���ꂽ��������BAI�R�}���_�[�Ƃ��Ė��O�ɕ��̃C�R����A���t���A���O�R���g���[�����s�����B�w��e�x�ƌĂ����̂��B�w��e�x�����͖��O�ɑ̐��ɋt�炤���Ƃ͔n���炵���Ǝv�킹�������B�n���őz�����邱�Ƃ̂ł���J����̐��E�́A�唼�����̎���̂��̂ƍl������B���������O�̓J����̂�������ł����Ȃ��������߁A�l�X�͐�����C�͂������A�����Ɂw�Q��x�悤�ɂȂ����B
KAFKA ( 1991 )[��] �M��F�J�t�J�^���{�̈��� by Steven Soderburgh[d]
It seemed that THEY forced to obey until THEY died....
�[�[�[�J����͂��̗L��l��[�����Ȃ��邱�Ƃ͂Ȃ��A�����m�I�����̕K�R�Ƒ����đ��푰�̖����ɂ������t����悤�ɂȂ����悤���B���Ȃ��Ȃ��̂̓J����̓����ł�����B���������ւ̎��M�̗��Ԃ��Ȃ̂��낤�B�J����ɂƂ��Ď��s�͖����ւ̗Ƃł�����B���s���Ƃ���Ƃ����_�ł͗D��Ă���̂�������Ȃ����A�ƍߎ҂Ƃ̐e�a���������̂ŎЉ�͂����ɑ������B�V�X�e���Љ�ɂ����Ă͎��s�͂P�O�O�_���_�̃e�X�g�Ō��_�����悤�Ȃ��̂ŁA���ꂪ�l�]���Ƃ��Ĉꐶ���ĉ�����B�����I�ɂ��̃q�G�����L�[�̒��Ő����邱�Ƃ���������B�s���߂����w���Љ�Ɠ����悤�Ȃ��̂ŁA���w���łȂ��ƌ�̐l���͎��s�������������B����ȎЉ�������t����ꂽ���͂��܂������̂ł͂Ȃ����A�J����͖��������Ƃ�����������o���Ă���Ƃ����s�v�c�Ȑ����������Ă������߁i���̍s�������̓J���炪�ǂ̂悤�ȑ��݂ł��邩���l�����ŏd�v���j�A�J����̎��E���ɓ����Ă��܂��ƕK�R�I�ɃJ����Ƃ̐킢���n�܂����B���Ă͖��]�L�̑��@�����ӎ푰�ɏP�����������悤���B
Reference >> |
a�D ^ Das Schloss ^ book:�@�O�c�h�� �� / �t�����c�E�J�t�J �� �w��x ISBN-13�F 978-410�Q�O�V1�O2�P b�D ^ Franz Kafka c�D ^ Kafka (the movie�j �M��F�w�J�t�J�^���{�̈����x by Steven Soderburgh d�D ^ Steven Soderburgh h. ^ AKIRA (The movie) i. ^ ��F���m e�D ^ Der Process ^ book:�@�҃Z�C �� / �t�����c�E�J�t�J �� �w�R���x ISBN-13�F 978-4�O03243824 f�D ^ The Trial�@�M��F�w�R���x by David Jones j. ^ Hangmen Also Die byFritz Lang[40] g�D ^ David Jones |